
キノコは秋のものという固定概念にとらわれている人はアミガサタケを見逃してしまう。 ちょうど桜の花が散り始める頃に庭先や林の中で発生する。蛇足ながら付け加えるとアミガサタケはフランス料理の食材の一つで結構な値段で取引されている。但し、生食すると中毒するので注意が必要である。
【特 徴】
キノコは全体に灰褐色で頭部と柄に分れる。頭部には網目状の助脈という隆起がある。
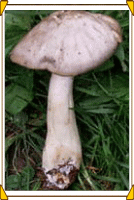
広葉樹あるいは松の混じる林内に転々と発生する。食用キノコのホンシメジやウラベニホテイシメジなどによく間違えられることがある。誤食すると胃のムカつきに始まり激しいおう吐や下痢、腹痛を起こす。
【特 徴】
傘は直径が7cm~16cmで始めは丸山形であるが後に開いて中高の扁平となり、縁は不規則に屈曲する。
ヒダは始めは白色であるが後肉色となり、柄は上生から直生で後に殆ど離生状になる。

晩秋の杉などの朽木や古いオガクズ、ゴミ捨て場に単生~群生する。
傘は小型で湿った時は暗肉桂色で乾くと中央部から明るい淡黄色になる。
柄は細長く中空で上部に不完全なツバがある。
中毒症状は、その名のように食後6~24時間後にコレラと同じく激しい下痢が起こり、1日ほどで一度回復するが、その後4~7日後に肝臓や腎臓などの臓器が破壊され、最悪の場合は死にいたる。
この症状はタマゴテングタケやドクツルタケなどと同じ症状であり、同じアマトキシン類によって引き起こされる。

梅雨期から秋にかけて各種広葉樹の枯れ木に発生する。よく似ているヒラタケは晩秋から春にかけての発生が多い。
【特 徴】
傘は始め饅頭形で開くと半円形になる。表面の色は淡灰褐色から淡黄色となり、湿っている時は弱い粘性がある。ヒダは垂生し、並び方はやや密、色は白色。柄は一般的に短く、傘の片方に偏ってつき色は殆ど白色に近い。
ヒラタケに比べて傘の厚みは薄く、肉も柔らかい。

広葉樹や針葉樹林内の地上に単生あるいは群生する。地味な色をしており、ヒメサクラシメジやホンシメジと誤食による食中毒が多い。誤食すると腹痛やおう吐、下痢などを起こすガ死亡例はない。
【特 徴】
傘は計が3cmから8cmで表面は赤褐色から栗色となり湿ってくると粘性がでる。
ヒダは白色で古くなると赤褐色のシミを生じ深く湾入し、密になる。
柄は上部が白色で下部が淡赤褐色になる。
ヒダに傷をつけると褐色のシミが出来るのが特徴である。

早いものは梅雨時から姿を見せはじめ、秋のおわり頃まで、コナラ、クヌギとアカマツの混ざった林の地上に点々とあるいは数本ずつかたまって発生する。秋のきのこシーズンになると必ずといってよいほどきのこ中毒がおきる。このクサウラベニタケはきのこ中毒の原因の代表格である。毒性はそれほど強くないので、命にかかわるような事にはならないが、中毒をした事のある人の話では、とにかく苦しいらしい。食用のウラベニホテイシメジと同じ時期、場所に生えるのでややこしい。ウラベニホテイシメジを食べて味をしめた人がひっかかりやすい毒きのこで、まったくの初心者よりも少しきのこの事がわかるかなといった段階の人は特に注意が必要である。
[特 徴]
傘の表面は灰褐色から灰色で乾くと絹糸状光沢があり、ひだははじめ白色で胞子が成熟するとピンク色になる。柄はつば、つぼを欠き、中空で指でつまむと容易につぶれる。

夏から秋にかけてアカマツ・コナラ林やモミの混ざった広葉樹林内の地上に発生する。ほかの白いテングタケ属のきのこと同様に有毒である可能性もある。
[特 徴]
傘は初め半球形で後にはほぼ平に開く。表面の色は白色で、とがったいぼが散在する。ひだは柄に離生し並び方はやや密で色は白色から淡黄色。柄も傘とほぼ同色で基部は紡錘形にふくらむ。きのこが成熟すると、部分的に淡赤褐色をおびる。

林内の地上から発生する全体が白色のきのこで、つばとはっきりしたつぼがある。
大半が有毒きのこのテングタケ科の菌。(シロオオハラタケ、シロマツタケモドキと類似)
発生場所:広葉樹林、針葉樹林の地上(単生)
発生時期:夏~秋
形態
かさ:5~10cm、白色 ひだ:白色
柄 :6~10cm、シロタマゴテングタケは白色でほとんどささくれは無いが、ドクツルタケはこのささくれがあるのが特徴
上部につばがつき、根元は袋状のつぼを持つ

夏から秋にかけてコナラ、クヌギなどの広葉樹林やシラビソなどの針葉樹林内の地上に点々と、あるいは列状に発生する。以前にはヨーロッパ産のタマゴタケと同一種と考えられていたが、最近の研究では別種とされるようになった。全体が非常に派手な色のために、はじめは気味悪がられるが、一度味を覚えると病みつきになるほどだという。ヨーロッパでは皇帝きのこと呼ばれ珍重されている。類似の毒きのこであるベニテングタケとはひだ、柄、つばの色が違うので区別は容易である。ただし毒きのこのタマゴタケモドキの中にはよく似た個体もあるので注意が必要である。
[特
徴]
傘は5cm~15cmで表面は鮮やかな未紅色で周辺部に放射状の模様がある。ひだ、柄、つばは卵黄色でとても美しく、柄にはオレンジ色のまだら模様があり、中空。つぼは袋状で白色である。

ブナやイタヤカエデなどの立ち枯れ倒木に多数な重なって発生する。
食用のシイタケやムキタケと誤って食べて中毒される方が多い。
おう吐や腹痛、下痢などを起こす。死亡例があり注意が必要である。
【特 徴】
傘は半円形~じん臓形で径は10cmから25cmと大きなキノコで初めは黄褐色のち紫褐色~暗褐色となり、ロウ状の光沢を帯びる。
ヒダは淡黄色~白色、柄に垂生して幅が広く発光性がある。
柄は傘の片方に付き太くて短い。
裂くと中心に黒っぽいシミがある。

別名をヒョウタケともハエトリタケともいう。ヒョウの様な斑紋のあるという学名そのままに傘の上につぼの名残りを付着させている。アカマツ林、トウヒ林、コナラ・クヌギ林などで夏から秋にかけてごく普通に見られる。これも毒きのこのひとつでその毒性はベニテングタケよりも強いといわれている。食べると大量に飲酒した時のようにおう吐したり気分が悪くなったりする場合もあるという。
[特 徴]
傘は初め半球形で最後には平らに開く。表面は褐色から灰褐色でつぼの名残がいぼ状に付着している。ひだは白色で離生する。柄にはつばとつぼを持ち、いずれも白色。つぼは時によると痕跡程度の事もある。

形態の特徴: キノコは中型、幼時は半球形、次第にまんじゅう形から平らに開く。カサの直径は4~7cmで、カサの表面はやや粘性があり、黄褐色から暗褐色、灰黒色のツボの破片が付着し、周辺部は淡色で放射状の溝線がある。ヒダは白色で縁は灰色粉状。柄は 9~15×8~13mm、基部から上方に向かって細くなり、表面は灰色の繊維状の小鱗片でおおわれ、ツバを欠く。柄の基部は袋状のツボをつくらず、不完全な輪を形成する。担子胞子は球形で、直径11~14μm、1個の大きな油滴を含み、非アミロイド。
発生時期:夏~秋
発生場所:ブナ科樹木
傘:弱い粘性有、条線有、いぼ散在
傘の下面:ヒダ、離生、密
柄:ツバなし、灰色の小鱗片有、ツボは不完全

夏から秋にかけて各種の広葉樹林、モミ林、ツガ林などの林内地上に点々と発生する。薄暗い林の中に真っ白なこのきのこが発生しているのを見ると、ドキリとする。純白の外見とはうらはらに、世界の猛毒きのこの中でも横綱格のひとつである。ヨーロッパでは「死の天使」の異名で恐れられている。その割に中毒する人が多いのは、野生のマッシュルームと見まちがえやすいためだと言われている。日本ではあまり食べる人もいないようなきのこであるが、何年かに一度は中毒事故があり、その中毒患者のうち何人かは命を落としている。
[特 徴]
傘、ひだ、柄、つば、つぼともに白色のきのこ。時として傘の中心部が紅褐色をおびる事もある。つばより下の柄はささくれにおおわれ、つぼは袋状で大型である。

広葉樹や針葉樹の切り株や倒木に群生する。食用のクリタケと間違う事があるが噛むと味が苦い。誤食すると胃のムカつきから激しいおう吐、下痢、腹痛を起こす。
【特 徴】
傘は径が1cm~7cmで硫黄の様な黄色
ヒダは初めは黄色で後に帯オリーブ緑色~暗紫褐色となり、柄に湾生、密
柄は繊維質で中空となり、傘と同じ硫黄の様な黄色

主に夏、林などの地上に発生する。
傘は灰褐色、ひだはクリーム色で傷つくと赤変する。
柄はほぼ傘と同色。猛毒で、クロハツと誤って食べて死亡した例もある。
クロハツは傷つくと赤変後、しばらくすると黒変するので区別できる。
発生時期:夏~秋
発生場所:マツ・コナラ、シイ・カシ林
傘:中央窪む、灰褐色
傘の下面:ヒダ、直生~やや垂生、疎、傷口赤変するが黒変しない
柄:中実

夏から秋のシラカバなどの広葉樹や針葉樹林に発生する。
古くから知られている毒キノコであり、消化器と神経系に症状が出る。
【特 徴】
傘は径が10cm~20cmと大ききて幼菌は球形であるが後に丸山形から扁平に開き、表面は真紅色~橙黄色で白いかさぶた状のイボがある。
ヒダは白色で柄に離生、密
柄は白色で上部に謨質のツバがあり、根元は球根状に膨らみ、ツバの残りが環状に残る。

毒はないがカビ臭くて食用は不可
夏から秋にかけて色んな林内の地上に発生する。発生は比較的まれであるといわれている。
原色日本新菌類図鑑によれば使用した学名が、このキノコの学名として適切であるかどうかは疑問が残るが、これまでの考え方に従うとしてあり、ここでもそれにもとずいて学名をつけた。
【特 徴】
土の上に埋まった菌の塊(専門的には菌核)から伸びた茎状の部分から10~20個ものウサギの耳状にキノコが発生する。
色は始め橙黄色であるがやがて黒くなる。乾湿の変化によるものか時々キノコの表面から胞子をとばす。

寒い時期を除いてほぼ一年中みられる。広葉樹の枯れ木上に群生するが、乾燥しているときは情けないほど縮んでいる。キクラゲの乾燥品として売られている場合も多い。
[特 徴]
きのこは耳形から円盤形などの多様な形になる。背面は灰褐色で、白色の細毛におおわれている。表面は暗褐色で滑らか。乾いた時には小さく縮み、湿ると水分を吸収して大きく広がる

秋にマツ林、カラマツ林、ブナ科の樹木の林内地上に発生する。ナメコと近縁なきのこで広く食用にされている。よく似たチャナメツムタケの方が食用きのことしては有名だが、このシロナメツムタケは、より淡泊な味である。
[特 徴]
傘は初めまんじゅう形で後には平らに開く。色は淡褐色から灰褐色で表面にささくれが着くこともあり、ぬめりもある。ひだは初め白色で後には淡黄土色になり並び方は密で柄に直生する。柄は傘とほぼ同色で根もとは茶褐色。表面にはささくれがある。

夏から秋に様々な森林下に発生する菌根菌。
傘は赤からピンク色。雨などによって色が落ち、白くなっていることもある。傘の表面の皮状になっていて容易にむくことが出来るひだは白色。
肉は白色でとても辛く無臭。硫酸鉄(Ⅱ)水溶液と反応しピンク色に変色する。
柄は白色。有毒。毒成分はムスカリン類、溶血性タンパク。本種は類似種が多いので同定が難しい。
その他:強烈な苦味がある

夏から秋にかけてブナやナラ類の枯れ木上に発生する。近縁のヌメリツバタケモドキは日本特産といわれていて、ひだに著しいしわがあることが特徴となっている。どちらのきのこも同じように食用になる。
[特 徴]
傘は初め半球形からまんじゅう形で後には平らに開く。表面の色は灰褐色から白色で強いぬめりがある。ひだは柄に直生からやや上生気味で、並び方はややあらい。色は白色。柄は淡紫褐色から白色で繊維質で固く、つばをもつ
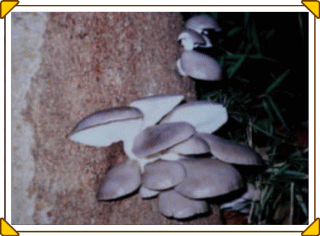
晩秋から春にかけて各種広葉樹の切り株や倒木上におり重なって発生する。ヒラタケというきのこは知らなくても一般に「しめじ」という名称で売られているきのこの事だといえば大抵の人は思い当たあたるにちがいない。分布はほぼ全世界であり、ヒマラヤ山麓でカンバ類の枯れ木上にたくさん発生しているのを見つけて天ぷらにして食べたこともある。野生の株は人工栽培されたものより歯ごたえ、味ともにずっとよい。
[特 徴]
傘は初めまんじゅう形で後に開いて半円形やじょうご形となる。色は初め灰青色から黒色で傘が開くと灰色から灰褐色、白色などになる。ひだは白色から灰色で柄に長く垂生する。並び方はやや疎からやや密まで変化に豊む。柄は短くきのこの中心についたり、片寄ってついたり、きのこの側面につく場合もある。
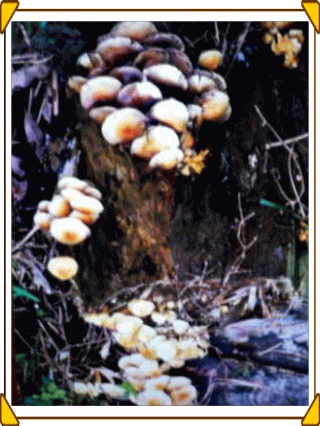
秋の半ば過ぎにブナ、ミズナラ、シラカバ、ハンノキなどの広葉樹の枯れ木上に多数が重なりあって群生する。「のどやき」、「かわふき」など地方によって様々な呼び名があり、それだけ広く利用されている食用きのこでもある。毒きのこのツキヨタケと混ざって発生することもあるが、ムキタケには暗黒下で発光するような性質はないので区別できる。
[特 徴]
傘は初め半球形やまんじゅう形で後には開いて形が腎臓型や半円形となる。色は黄褐色のものが多いが、緑色や紫色を帯びることもある。表面には細かい毛を密生する。表皮ははがれやすい。ひだは淡黄色から淡褐色で並び方は密で柄に接する部分で終わる。柄は淡黄褐色からほぼ白色で傘の横につき、太く短い。